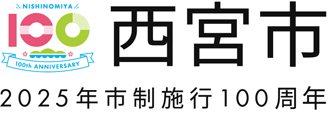ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)の予防接種
更新日:2025年4月1日
ページ番号:78761714
概要
ヒトパピローマウイルス(HPV)は皮膚や粘膜に感染するウイルスで、100種類以上あります。
このうち主に粘膜に感染する種類は、性行為を介して生じる表皮の微少なキズから、生殖器粘膜に侵入して感染するウイルスであり、海外においては性活動を行う女性の50%以上が、生涯で一度は感染すると推定されています。
粘膜に感染するヒトパピローマウイルスのうち少なくとも15種類は子宮頸がんから検出され、「高リスク型ヒトパピローマウイルス」と呼ばれています。
高リスク型ヒトパピローマウイルスの中でも16型、18型とよばれる2種類は特に頻度が高く、海外の子宮頸がん発生の約50~70%に関わっていると推定されています。
HPV未感染者を対象とした海外の研究では、感染や前がん病変の予防にワクチンが効果的であることが示されています。
対象者
小学校6年生から高校1年生相当年齢までの女子(12歳となる年度から16歳となる年度の末日まで)
注意
- 標準的な接種スケジュールで接種する場合、合計2回又は3回の接種を完了するまでに最短でも6か月必要です。
- 標準的な接種スケジュールですべての接種を公費負担(無料)とするためには、16歳となる年度の9月末までに1回目の接種を開始する必要があります。
キャッチアップ接種等の接種期間の延長について
キャッチアップ接種の対象者(平成9年度~平成19年度生まれ)、および2008年度(平成20年度)生まれの女子で、2022年(令和4年)4月1日~2025年(令和7年)3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種している方は、接種期間が延長されています。
詳しくは以下をご確認ください。
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)の予防接種の接種期間の延長について
標準的な接種期間
中学校1年生(13歳となる年度の初日(4月1日)から、当該年度の末日(3月31日)まで)
接種方法
ワクチンの種類により接種間隔が異なります。
ワクチンの種類
ワクチンは以下の3種類があります。
- 2価ワクチン(製品名:サーバリックス)
- 4価ワクチン(製品名:ガーダシル)
- 9価ワクチン(製品名:シルガード9)
留意事項
- 決められた間隔をあけて、合計3回接種します。
(9価ワクチンを小学6年~15歳未満で接種する場合のみ2回) - 原則、過去に接種歴がある場合は、同一の種類のワクチンを使用します。
- 定期接種として2価ワクチン・4価ワクチンを未完了(1回、または2回のみ接種)の方が、9価ワクチンでの接種完了を希望した場合は、原則として過去に接種したものと同一のワクチンで接種することが望ましいですが、医師とよく相談の上、9価ワクチンを接種することは差支えありません。
- ただし2価ワクチン・4価ワクチンの互換性に関する安全性、免疫原性、有効性のデータがないため、2価ワクチンと4価ワクチンの併用はできません。
接種間隔
| ワクチン/製品名 | 標準的な接種方法 | 左記をとることができない場合の接種方法 (最低限必要な接種間隔) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2回目 | 3回目 | 2回目 | 3回目 | ||
| 2価/サーバリックス | 1回目から1月 | 1回目から6月 | 1回目から1月以上 | 1回目から5月以上 かつ2回目から2月半以上 | |
| 4価/ガーダシル | 1回目から2月 | 2回目から3月以上 | |||
9価/シルガード9 | 15歳以上 | ||||
小学6年~15歳未満 | 1回目から6月 | - | 1回目から5月以上 | - | |
※1:接種を開始した年齢により、接種回数が異なります。
※2:1回目から1月以上5月未満で接種した場合は、3回接種となります。(2回目と3回目の接種間隔は3月以上)
委託医療機関及び実施方法
- 市が委託している医療機関に直接ご予約のうえ、接種を行ってください。
- 予診票は、医療機関にて配布しておりますので、当日ご記入ください。
- 予防接種番号が不明な場合は、保健予防課(0798-35-3308)までお問い合わせください。
- 委託医療機関及び実施方法の詳細についてはリンク先を確認してください。
接種を検討されるにあたって
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)の予防接種は、その有効性と接種による副作用(副反応)が起こるリスクを十分に理解したうえで受けるようにしてください。
予防接種の有効性とリスク、その他の関連情報などについては、以下の厚生労働省のホームページに掲載の資料などをご参照ください。
ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(外部サイト)![]()
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)の予防接種後に生じた痛み等症状について
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、接種後に痛み、しびれ、脱力、その他異常な症状があるときは、すみやかに接種した医療機関の診察を受けてください。
また、厚生労働省および兵庫県において、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)の予防接種後の副反応(主として痛み、しびれ、脱力など)について被接種者とそのご家族に対して適切な医療を提供するための体制が整備されています。
相談窓口や、協力医療機関についての詳細は、以下の厚生労働省および兵庫県のホームページをご覧ください。
兵庫県における協力医療機関
- 神戸大学医学部附属病院
- 兵庫県立尼崎総合医療センター
- 兵庫県立はりま姫路総合医療センター
協力医療機関での受診を希望される場合は、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)の予防接種を受けた医療機関で接種後の症状について受診してください。
その後当該医療機関の医師から、協力医療機関へ紹介するという手続きとなります。
健康被害救済制度
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく健康被害救済制度により、補償を受けることができます。(過去に任意接種として接種した予防接種は対象外)
医師の診断に基づき、予防接種健康被害救済制度の申請をする場合は、西宮市保健予防課(0798-35-3308)までご相談ください。
【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部サイト)![]()
【厚生労働省】ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について(外部サイト)![]()