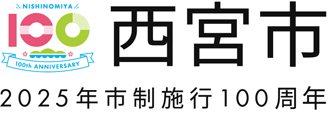骨粗しょう症を予防しましょう
更新日:2025年9月16日
ページ番号:12536052
毎年10月20日は世界骨粗鬆症デーです!
世界骨粗鬆症デー(WOD)は、1998年に国際骨粗鬆症財団(IOF・本部スイス)と世界保健機構(WHO)が共同により骨粗鬆症と骨代謝障害の啓発を目的として制定されました。「世界中から骨粗鬆症による骨折をなくす」ことを目標に世界規模でキャンペーンを展開しています。
骨を守るためには日々の心がけが大切です。この機会にご自身の骨にも目を向け、骨粗しょう症を予防していきましょう。
<参考リンク> 厚生労働省ホームページ 骨活のすすめ(外部サイト)![]()
目次

骨粗しょう症とは、骨量(骨密度)が減る、または骨の質が低下することで骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気のことをいいます。
初期症状はありませんが、次第に背中や腰に痛みがでたり、背丈が縮んだり、骨折しやすくなります。
高齢者の介護が必要となった主な原因として「骨折・転倒」が13.9%と、認知症・脳卒中についで3番目に多い原因となっています。( 厚生労働省 令和4年国民生活基礎調査 )

妊娠・授乳により子どもにカルシウム等の栄養素が運ばれることや、閉経により骨の破壊を抑える女性ホルモンが減少することから女性は男性よりもリスクが高くなります。
また、糖尿病や腎臓病などの生活習慣病の方ではカルシウムが吸収されにくくなったり、骨の形成の低下が起こり、骨粗しょう症になるリスクが高まると言われています。
そのほか、骨粗しょう症のリスクを高める要因として、喫煙、お酒をよく飲む、運動不足、偏食、痩せすぎ、遺伝などがあります。

1.骨に良い食事をとりましょう
カルシウムを多く含む食品をとる。
骨の主成分となる栄養素ですが、意識して摂取しないと不足しがちな栄養素です。慢性的に不足すると骨がもろくなってしまいます。
カルシウムを多く含む食品 : 牛乳、乳製品、大豆製品、緑黄色野菜、小魚、海藻類
サプリメントや補助食品を利用する際は1日の目安量を守り、過剰摂取に気を付けましょう。
カルシウムたっぷりレシピは、バランス食レシピ集をご覧下さい。

ビタミンD、ビタミンK、マグネシウムを多く含む食品をとる。
カルシウムの吸収を助けるビタミンD、骨への吸収を助けるビタミンK、骨の形成に関わるマグネシウムを合わせてとることも強い骨を維持するために重要です。
ビタミンDを多く含む食品 : 干ししいたけ、青魚、うなぎ、鮭など
ビタミンKを多く含む食品 : 納豆、ブロッコリー、ほうれん草など
マグネシウムを多く含む食品 : 牛乳、小魚、ひじき、大豆、ごま、ほうれん草、アーモンドなど
リンや食塩の摂り過ぎに注意する。
リンは摂り過ぎるとカルシウムと結合して吸収を妨げます。食塩も摂り過ぎるとカルシウムの尿への排出を促します。リンや食塩は加工食品に多く含まれているので食べ過ぎには注意しましょう。
アルコールやカフェインの摂り過ぎに注意する。
お酒に含まれるアルコールやエナジードリンク、コーヒーなどに含まれるカフェインは利尿作用があり、摂り過ぎるとカルシウムを排泄しやすくなります。
食事についての詳細は、改善しよう!食事編をご覧ください。
2.適度な運動をしましょう
骨は負荷がかかると強くなろうと骨量が増加し、負荷がかからないと骨量は減少し、弱くなります。
軽い負荷の運動でも、こまめに運動することにより効果が得られます。
さらに、屋外に出て適度に日光に当たることでカルシウムの吸収を助けるビタミンDが体内でつくられます。
運動についての詳細は、改善しよう!運動編をご覧ください。

3.定期的に骨密度をチェックしましょう
骨粗しょう症は早期発見・早期治療が大切です。
西宮市では、リスクの高い30歳以上の女性を対象に骨粗しょう症検診を実施しています(900円、70歳以上は無料)。
詳しくは「西宮市 骨粗しょう症検診」をご覧ください。
集団会場の「女性のための検診」では管理栄養士・保健師・助産師による健康相談を併設しています。ご活用ください。
また各保健福祉センターでは各種相談事業を行っています。詳しくは「各種健康相談」をご覧ください。